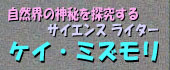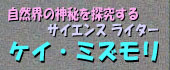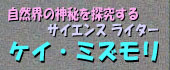

|

 宮崎駿アニメに投影される社会風刺とスピリチュアル 宮崎駿アニメに投影される社会風刺とスピリチュアル
2008年9月 |
|---|
○児童アニメ? 難解すぎる児童アニメ? 大人向けアニメ?
2008年7月19日、宮崎駿監督のアニメーション映画『崖の上のポニョ』が公開された。子供たちの夏休みが始まる時期に公開された同作品は、『となりのトトロ』(1988年)と似て、他作品よりも子供たちに親しまれるストーリーとキャラクターで構成されていた。だが、『風の谷のナウシカ』以来、宮崎氏が原作・脚本・監督を手掛けた長編映画は、子供でも楽しめるものの、子供には難解すぎる深いメッセージが含まれてきたと言えよう。そして、それは『崖の上のポニョ』においても、例外ではない(のちに詳述)。
初期の作品から一貫して垣間見られることは、愚かな人間による対立や環境破壊を風刺しながらも、「愛」をキーワードとして、打開策を考えさせる点にあると筆者は考える。そして、各作品で提示された打開策は、初期の作品から最新の作品までの間に、少しずつ変化してきたように思われる。それは、1980年代から現在までの<神秘・スピリチュアル>の動向をそっくり反映しているように思われるのだ。
そもそも、漫画やアニメーションの世界では、実写では困難なファンタジーを描きやすい側面もある。そのため、神話や伝説を土台に、神秘的なミステリーや奇跡を交えてストーリーがスピリチュアルに描かれるケースは珍しくない。そのため、多くの漫画家やアニメーターはある程度そのような下地を備えている。
本稿では、宮崎監督作品におけるストーリーの組み立てとその変遷は、本人がたとえ意識していなくても、近年の<神秘・スピリチュアル>の動向に呼応している点を明らかにしていきたい。
○自然破壊を毅然と批判
一般的に、宮崎氏の才能が大きく評価されたのは、『ルパン三世 カリオストロの城』(1979年)の脚本・監督を手掛けたことに始まるとされる。宮崎氏の作品の傾向を語る上で、本稿では、原作・脚本・監督のすべてを手掛けた長編アニメーション作品だけに限定してみることにした。それらを順に上げると、『風の谷のナウシカ』(1984年)、『天空の城ラピュタ』(1986年)、『となりのトトロ』(1988年)、『紅の豚』(1992年)、『もののけ姫』(1997年)、『千と千尋の神隠し』(2001年)、『崖の上のポニョ』(2008年)となる。但し、『紅の豚』に関しては、宮崎氏が幼い時から空を飛ぶことに憧れていた個人的な夢が投影された、中年男性向けの例外的な作品という面もあり、敢えて本稿では除外しておく。
残された作品の中で、『風の谷のナウシカ』、『天空の城ラピュタ』、『となりのトトロ』、『もののけ姫』を、宮崎氏の初期のスタンスを反映する作品群と捉えたい。そして、『千と千尋の神隠し』を次なるスタンスの作品、『崖の上のポニョ』を最新のスタンスの作品と分類してみたい。つまり、原作・脚本・監督を行った最近の二作品が大きな意味を持ち、その二作品から変化を感じ取れるのである。
では、初期の作品群に反映されているテーマを考えれば、現代文明の闇、環境破壊による代償、人間の愚かさなど、教訓を与えるような側面が垣間見られ、アニミズム回帰を示唆するかのような印象を与える。アニメーションは子供のものと言いながらも、宮崎氏は、難解すぎる児童アニメ、或いは、大人向けアニメを作ってきた感が否めない。
少し具体的に振り返ってみよう。例えば、『風の谷のナウシカ』のあらすじは次のようなものだ。かつて人類は自然を征服して繁栄を極めたが、「火の7日間」と呼ばれる大戦争で文明は壊滅した。それからおよそ千年、わずかに生き残った人類は、有毒な菌類からなる森()に征服されようとしていた。人々が嫌う巨大な蟲(むし)・王蟲(おうむ)は、実は汚染された世界を浄化するために毒を体内に取り込み、森を守っていたことを主人公ナウシカは悟る。無知な権力者らは王蟲を攻撃することで、危機を回避しようとするが、ナウシカは人柱となってそれを阻止しようとした。すると、王蟲は怒りを解き放ち、ナウシカを復活させる奇跡が起こる。
また、『天空の城ラピュタ』のあらすじはこのようなものだ。かつて飛行石を利用して、空中に浮遊する城「ラピュタ」が存在し、高度な科学技術を持ったラピュタ人が地上世界を支配していた。伝説のラピュタが実在したことを知った政府の特務大佐ムスカは、ラピュタを独占し、世界の支配者になろうとした。そのために、ラピュタ人の子孫である少女シータが持つ飛行石ペンダントとラピュタに関する知識を求めて、彼はシータを誘拐する。だが、ラピュタの科学技術と財宝が邪悪な者の手に落ち、世界に闇が訪れることを危惧したシータは、滅びの呪文を唱えて、ラピュタを滅ぼすことにした。
一方、『となりのトトロ』においては、前二作ほど、人類の文明が生み出した闇を抉り出すほど、スケールの大きなものではないが、田舎に残された自然環境には、何か神秘的な存在を見出すことができる点を示唆しており、環境問題に対する関心は反映されている。
そして、『もののけ姫』であるが、これは未完のまま映画化した『風の谷のナウシカ』を完成させた映画と見ることも可能で、テーマには共通点が感じられる。シシ神の森を破壊して砂鉄や材木を得る人間たちと、シシ神の森を守る獣たち、そして山犬に育てられたサンとの間に、壮絶な争いが繰り広げられる。ついにシシ神は人間に首を切られると、触れるものすべての命を奪い取る巨人ディダラボッチに姿を変えて、人間を襲い始める。怒りを収めるために、サンと主人公のアシタカは切られた首をディダラボッチに返すと、森の一部は元の姿を取り戻す。そして、人間を憎んだサンと、人間のアシタカは共に生きようと励ます。
この初期の宮崎作品に見られる共通項は、自然環境を破壊することで自らの首を締める人間の愚かさを風刺しながら、自然との共生を強く求めていることかもしれない。それは、寛大な愛を持ちながらも、主人公は敵に対して毅然とした態度を示すことに象徴されるだろう。しかしながら、宮崎氏の人間好きは随所に現れている。どうしても憎めない、愛嬌のある存在が人間であるという側面が垣間見られるのだ。
○愛の法則で対立を止揚する
『千と千尋の神隠し』は、それまでの宮崎氏の作品と異なり、大きな飛躍と発展が窺える。自然との共生というテーマから離れている点もあるが、人類が抱えてきた問題点に対する対処法に、新たな視点を与えたように感じられる。まずは、簡単にあらすじを振り返ってみよう。
主人公の少女、千尋(ちひろ)は両親とともに引越先に向かう途中、森の中の不思議なトンネルに迷い込む。トンネルの向こうには草原があり、その先に無人の町があった。そこは神々が病気と傷を癒すための温泉町であり、千尋の両親は、神々のための食事を食べてしまい、呪いを掛けられ、豚にされる。一人残された千尋は、謎の少年ハクの助けを得て、両親を助けるべく、まずは、湯屋を経営する強欲な湯婆婆の下で働くことになる。ひ弱だった千尋は意外にも奮起して、「千(せん)」の名で湯屋で働き、客の魂を解放に導く。さらに、自分を助けたハクの危機を救い、湯婆婆への献身も忘れず、最終的には、両親を返してもらい、人間の世界へと戻っていく。
さて、本作品だが、実に興味深い解釈が可能であり、筆者はウォシャウスキー兄弟監督作品『マトリックス』に通じる面もあると考える。『マトリックス』においては、我々が生きているこの世界は、実はコンピューターが創造した仮想世界で、我々は檻の中で夢を見せられているだけだという恐るべき真実を告げられる設定がある。
どこに類似点があるのかと言えば、異様な神々が集まる湯屋のある非人間の世界が、実のところ、現在の我々が暮らしている世界を反映している点である。湯屋は現代社会の縮図であり、我々は権力者の下で、生きていくために、あくせく働き続けねばならない。
これが白昼夢ではないことは、最後にトンネルを出て、人間の世界に戻った際、停めておいた車の中にたくさんの枯葉が入り込んで、汚れていたことでほのめかされていると言えるだろう。つまり、現実に長い時間が経過していたこと、又は、一種の<浦島現象>を体験したことで、体験が現実であったことを焼き付けているからだ。そして、それに気付いているのは、純真な心を持った子供だけであり、常識に目が曇らされた大人には分からない(『となりのトトロ』においても、子供だけが見られる<まっくろくろすけ>が登場する)。
しかし、筆者がここで指摘しておきたいことは、これまでの宮崎作品と異なり、敵と思われる相手に対して主人公が毅然と接するのではなく、むしろ同情心をもって大きな愛で包み込むことで、対立を解き解し、危機を乗り越えるアプローチを示していることである。
このような主人公の姿勢は、近年のスピリチュアルの世界では、非常に重要視されるものである。相手の意識を直接変えようとすることは不可能に近いものの、恨みたくなる相手に対してこそ、愛を傾けられるように自分の意識を変える(相手と一つになる)ことで、自ずと相手が変わるという奇跡が起こる法則が採用されているように思われるのだ。そのような意味で、『千と千尋の神隠し』は、ある意味で、完成形の雛型とも言えるだろう。
○楽天的な変化か?
さて、『千と千尋の神隠し』(2001年)において、既に完成の域に達した感がある宮崎作品であるが、その後の作品がどのようになるのか、筆者にとっては関心の的であった。その後、原作は別だが、宮崎氏は『ハウルの動く城』(2004年)の監督を行い、ストーリーの中で新たに<魔法>を登場させた。そして、その<魔法>の真意は、原作・脚本・監督をすべて務めた最新作『崖の上のポニョ』で説明されるのかもしれないと思われた。
冒頭で触れたように、本作品は、子供向けの趣が強い。しかし、中編作品を長編作品に変更した『となりのトトロ』ともだいぶ異なる。かつてのようなストーリー性は解体されているものの、<魔法>が登場し、かなり計算された展開となっている。
魚の子供であるポニョは、瓶に入り込んで動けなくなったのを少年・宗介に助けられて名付けられた名前。ポニョの父親フジモトは、かつては人間だったが、その破壊性に愛想を尽かして海の(一族)として暮らす魔法使いである。フジモトはポニョを取り戻すが、人間になりたがるポニョは宗介に会うべく、家出する。フジモトは荒波を起こして、ポニョを海に連れ戻そうとするが、それにより人間の暮らす町が海に飲み込まれる。ポニョの母親は海の女神のような存在で、フジモトの行動にも、ポニョの希望にも、人間に対しても、寛大な姿勢を示す。
過去の作品で共通して見られるように、人間の愚かさに愛想を尽かせたキャラクター(フジモト)が登場するが、それでも人間好きで、人間の可能性に光を見出したい宮崎氏の一面が垣間見られる。
『千と千尋の神隠し』からややスタンスを変えたのかと思われる点は、危機に直面した際、その解決のための具体的なゴールに向かって必死に努力して、その主体的な努力が報われるというよりも、むしろ、純粋な心を持った人間は自ずと解決策が魔法のように与えられる印象を与える点である。また、5歳の宗介は心の優しい少年であるが、両親の名前を呼び捨てで呼ぶ。かつての古き良き時代を想起させるような回顧的な傾向はなく、非常に現代的である。ストーリー性がある程度解体されている点もあるが、何らかの根拠に基づいて行動を起こすよりも、起こった出来事に対して何かを考える猶予は与えず(必要は無く)、ただ現実を受け入れ、意識は常にその先に向けねばならないというメッセージも感じ取れる。『千と千尋の神隠し』と比べると、やや楽天的な未来を子供たちに託しているようにも思われるのだ。
○<神秘・スピリチュアル>な解釈
現在、我々は未来のことを考えると、文明を高度に発展させる以前に、地球環境がもつのかどうか、そのあたりを懸念せねばならない状況になった。しかし、かつて存在した終末論的な悲愴感は、解消したかのように思えるのは筆者だけであろうか。
1970年代後半から1980年代前半頃まで、宇宙に向けた我々の関心はポジティブで明るいものであった。当時の映画は、ジョージ・ルーカス監督の『スターウォーズ』シリーズや、スティーブン・スピルバーグ監督の『ET』・『未知との遭遇』などに代表されるかもしれない。
だが、宇宙へ向けられた大衆の明るい期待感はその後萎んで行く。UFOアブダクションの深刻な側面が話題として持ち上がっても、アメリカ政府は矛盾に満ちた説明でお茶を濁し、市民の政府に対する不信感は加速する。環境問題への意識も芽生えており、90年代後半までノストラダムスを代表とした終末予言や終末思想が広まった。この当時、まさに人間など滅んでしまって当然なのだという思想すら存在し、アニミズム的な自然回帰が口にされる時代だったように思われる。宮崎氏の初期の作品群は、このような時期に映画化され、非常に深刻なテーマに対して、正面から真面目に取り組んできたように思われ、接点のようなものが感じられる。
しかし、その後は、<神秘・スピリチュアル>の世界では、状況が一変する。チャネリング情報が人気を集め、1990年代後半になると、地球人類を破滅に導いてきた闇の宇宙人種(アヌンナキ)が改心して、地球のアセンション(次元上昇)が約束されたというメッセージが出回り始めたのだ。そのように確認不可能な情報には懐疑的ながらも、政治的な陰謀を暴露するような情報に関しては、現実世界において実際に反映されてきた流れを受けて、まんざらすべてを否定する訳にはいかないだろうという印象を持たれた方々も多かったのではなかろうか。
<神秘・スピリチュアル>情報を耳にしていた人々にとっては、ノストラダムスの予言を知っていながらも、20世紀末を迎える前にオカルト的な不安は解消されていたとも言える。そして、特別に心理的な動揺もなく21世紀を迎え、大きな変化もなく、しばらく現状維持が続くという認識があった。つまり、<神秘・スピリチュアル>な期待も不安も無く、あくまでも自助努力なくしては、人類の危機は解消されないという自覚があったように思われる。これは、1995年のオウム事件以降に対応し、日本ではオカルト情報には距離をおいて接するようになり、人々が現実的な思考に立ち返った頃に相当する。筆者にとって、極めて完成度の高い『千と千尋の神隠し』が製作されたのは、このような流れを経た時期である。
ところが、その後数年経つと、占いやスピリチュアルのブームが再来し、かつてのオウム事件など、まったく忘れられてしまったような状況となった。そして、アセンションという言葉が抵抗なく浸透するようになり始めた、まさに現在である。
過去の<神秘・スピリチュアル>を見てきた筆者には、やや危うい雰囲気すら感じるバブル期とも思える時代であるが、宇宙人や地底人の直接関与(ファースト・コンタクト)により、他力本願で現実世界が変革され、地球と人類が復興(アセンション)するものと期待する人々すら増えている。
そのような世相を反映するかのように、『ハウルの動く城』に続いて、<魔法>を登場させた『崖の上のポニョ』が製作された。『千と千尋の神隠し』においては、人類が抱えている問題に対して、愛の原理を持ち込むことで止揚(しよう)するスタンスが窺われた。宮崎氏のスタンスにまったく変化はないのが真相かもしれないが、見る者にとっては、自助努力による解決よりも、純粋な心を持った人々には自ずと外部から奇跡的な介入(魔法)が加わるという印象すら与えるものだ。そして、その変化を起こすのは、子供(インディゴ・チルドレン、クリスタル・チルドレン)である(海が人間の町を飲み込んだ際、古代魚で溢れかえった点も、原始の環境が回復されたことを暗示させる)。
漫画家やアニメーターは、ファンタジーを好み、超常現象、神話、伝説、神秘、スピリチュアルには造詣が深い。筆者からすれば、宮崎氏は敢えて最近の世相を反映させた作品を製作したのではなかろうかと思われるのだが、読者はいかが思われようか?
|
Back
ホーム | 最新情報
| 農園
| イベント | DVD/CD
| 執筆ポリシー | 著書 | 訳書等 |
記事 | 掲示板 |
リンク
|